1979年4月7日(土)は私と家族にとってオーストラリア体験の初日であったため、いまも鮮烈なビジュアル画像として私たちの記憶に残っている。成田空港からのカンタス航空シドニー行き夜行便は、約8時間後に明け染めた空の下に広がるシドニー国際空港に着陸した。すると間もなく2名の検疫官が無表情で乗り込んできて、キャビンの前方から後方までスプレーで乗客の頭上に向かって消毒液を散布し始めた。この時代のオーストラリアやニュージーランドでは、外来病原菌や害虫に対する防御のためであれば、旅客の不快感など問題外であったようだ。その後、私たちは飛行機を降りて空港ターミナルに進み、厳しい入国審査を受ける緊張の瞬間を迎えた。その時、消毒液の臭気がようやく薄れたこともあり、建物外部の方向から漂ってくる植物質の爽快な薫りを感じた。これがユーカリから発せられる薫りであり、オーストラリアで目立つ大きな樹木の大部分がユーカリであることを気付かせる体験であった。当時は日豪経済協力が急速に進んでいたが、一般の日本人にとっては遠い未知の国であり、一般的な情報はほとんど手に入らない時代であった。
私が勤務したオーストラリア国立大学(ANU)は首都キャンベラにある。英国植民地時代のオーストラリアではシドニーとメルボルンが大都市に発展していたため、独立国家の首府を両市の中間に設置することとし、アボリジニーの言葉で「出会いの場所」を意味するキャンベラと命名された。その後、国際コンテストで斬新な都市計画を採択し、半世紀以上の時間をかけて建設を進め、1960年代後半にようやく初期計画の完成が宣言されたのである。合理的に計画されたこの街では歩行者と自動車の動線が完全に分離していて、幼子をかかえる私たちには本当に安心できる居住環境であった。私たちの住居は「5 Hopegood, Garran, Canberra」の職員用集合住宅であったが、庭先と外の緑地が一体となって広がっていて、ところどころに大きなユーカリの木が配置されていた。この場所の現在の様子はグーグルマップによって手に取るように見る事が出来る。キャンベラは東京23区の広さに30万人程度の人が住んでいて、中心部には人工湖(バーリーグリフィン湖)やブラックマウンテン、マウントアインズリーなどが配置され、その周辺には自然林緑地が広がっている。その一角を占めるANUのキャンパスは、大きなユーカリの木々の間をさわやかな風が吹き抜け、カラフルなインコや小鳥が飛び交う美しい光景が当たり前のように存在する場所である。
私がANUのクロウ教授から依頼された研究の対象は、グランディスというユーカリが大量に生産しているG−インヒビターという発根阻害物質であった。グランディスはローズガムという俗名で一般の人にも有用な大木として知られている。ユーカリは、実際には700種以上に分類されるフトモモ科ユーカリ属植物の総称であり、形態や成分は実に多種多様である。温暖地を好むグランディスは30メートル以上の直線的な巨木となるだけでなく、木質が適度に軟かくて加工しやすいので産業的に重要視されている。ところがユーカリは広範囲の異種間で容易に交雑してしまうため、種子から良質のユーカリ品種を育成するのは非常に難しい。そのため、当時のANUでは優れた性質のグランディスを挿し木や接ぎ木でクローン苗にする技術の可能性を検討していたのである。
オーストラリアは乾燥・高温にさらされる厳しい気候が支配的な大陸であるため、独特な環境適応能力を獲得した固有の生態系が成立している。オーストラリアの森林に入る場合には「トータル・ファイア・バン」という情報に注意を払う必要がある。これは、暑い日に屋外での火気使用を厳禁する一種の戒厳令で、気温が高く乾燥した日には山火事が極端に発生しやすいことを示しているのだ。オーストラリアにはブルーマウンテン、ブラウンマウンテン、レッドヒルなどという地名が数多く見受けられるが、暑い日に山林のユーカリが大量の精油成分を放出して太陽光線の一部を吸収するので、山林の遠景が色づいて見えるためと言われている。そのときの山林全体はガソリンを撒いたような状況となり、小さな火種から爆発的に燃え上がって大規模な山火事となる。面白い事にオーストラリア原生のフトモモ科(ユーカリ、カリステモンなど)、ヤマモガシ科(バンクシア、マカダミアナッツなど)、マメ科(アカシア、ミモザなど)の樹木は、いずれも山火事を利用して勢力拡大を図るという生存戦略を採用している。例えばユーカリの樹皮の下には普段は発芽しない無数の休眠芽があり、火災の際には精油成分の効果で表面だけが焦げる。すると休眠を誘発していた樹皮内の物質が消失し、次の降雨によって動物の体毛のように密集した芽を一斉に吹く(写真1参照)。また、バンクシアやアカシアなどの種子は、炎にあぶられて加熱されると発芽の準備が整う。これらの驚くべき環境適応により、オーストラリアの自然林は黒焦げになっても数年で元の姿に戻るのである。

ANU化学科のクロウ教授と植物学科のペイトン博士は、ユーカリを全く知らなかった私に辛抱強く正確な知識を与えてくれた。この頃、ペイトン博士はユーカリ専門家として、コアラの餌になるユーカリが日本で栽培可能であるかを豪政府の依頼で調査していた。その結果を受けて、5年半後の1984年10月に東京・名古屋・鹿児島の3都市でコアラを公開飼育する事が許可されたのである。また、一般のオーストラリア人がユーカリの薫りや精油成分をいろいろな形で日常生活に取り入れている事も教えられた。例えば、ユーカリ蜂蜜、キャンディー、湿布薬、化粧水、入浴剤など多種多様である。このような生活環境は、それまで植物に対して無関心であった私の感性を根底から変えることになったのである。
ところで、この国の人々が愛唱する「ワルチング・マチルダWaltzing Matilda」という歌曲は、英語の堪能な人が歌詞を読んでも全く理解できないはずである。私もこの歌の題名が「ズタ袋担いで行こう」という意味であると聞いて、オーストラリアの俗語(オージースラング)と英米語とのギャップに驚いたものである。冒頭のフレーズ、”Once a jolly swagman camped by a billabond, under the shade of a coollibah tree…..” は、「昔、陽気なswagman(放浪者)がbillabond(池)のほとりのcoollibah(ユーカリ)の木陰でキャンプした・・・」という意味なのだ。この歌全体がオージースラングで表現されていて、「警官に追いつめられて池に飛び込んだ羊泥棒の幽霊を偲ぶ」というペーソスに溢れたストーリーを独特な情感の曲に仕立てている。これがユーカリの薫りが育んだオーストラリア人の感性を表現するものであり、そのために50年前の名画「渚にて」のサウンドトラック曲にオーストラリアを象徴する曲として採用されたのであろう。
ユーカリは温暖湿潤な日本で栽培するとオーストラリアの数倍のスピードで成長する。このため、焦土と化した戦後の都市を復興し緑化するためにユーカリの植樹が推奨された時代があった。ところが、日本ではユーカリが容易に水分や養分を吸収できるため、根を十分に張らないうちに巨木に成長する。このことが台風シーズンに倒木被害を多発することになり、ユーカリが日本の都市緑化の舞台から降りることにつながった。また、ユーカリの薫りとなる精油成分などの生産量が極端に低下することも判明した。つまり、ユーカリは激しい気候のオーストラリアの大地に育つことによって本来の生き方ができるのであり、日本の優しい環境では単なるウドの大木に成り下がってしまうのである。なんだか身につまされるユーカリの生態である。
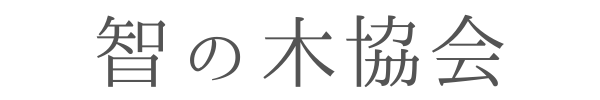
コメント