植物は、様々な形で人類に利用されている。一つの栽培植物でも、多くの場合、複数の用途がある。例えば、木綿の繊維を得るための綿でも、その実から食料油を絞っている。しかし、ビールの苦味付けに使われるホップは、ただビールのためだけに栽培されていると言っても過言ではない。
ホップは、20ヵ国以上で栽培され、その作付面積は約60,400haで、118,400t収穫される(2018年)。主な生産国は、アメリカ(49,200t)、ドイツ(41,800t)、中国(7,000t)、チェコ(5,100t)、ポーランド(3,200t)、スロベニア(3,000t)である。ホップの栽培にはワイン用ブドウ栽培と小麦栽培と中間の平均気温が必要で、栽培地は南半球を含めて緯度35-55度の地域に集中している。例えば、ドイツのホップ産地であるドイツ南部では、ホップ栽培とブドウ栽培が拮抗し、ブドウ畑の隣がホップ畑となる場合もあった。このため、ホップのべと病などの防除に、ブドウ栽培のボルドー液(アルカリ性の硫酸銅液)が転用された。日本のホップ生産は、主に長野県以北の岩手県、山形県などで行われている。生産量は、1989年の約1,900tをピークに減少続け、2010年代は約300tとなり、2018年には200t余りとなった。
世界中で栽培されているホップの原産地については、地中海の沿岸、西アジアから中央ヨーロッパなど諸説がある。ノアの箱舟が漂着したといわれるアララト山には、野生ホップが自生していて、原産地ではないかと言われた時代もあった。近年、英国のニーブは、「ホップの起源は中国である」と述べている。ホップの近縁種であるカナムグラが極東の日本、中国、台湾あたりでしか自生していないことも、ホップ中国起源説を支持している。ホップは、東アジアで飲料や食品の防腐剤として用いられ、東ロシアを経由してヨーロッパに伝えられた。ヨーロッパに伝わったホップは、直ぐにビールに使われた訳でははい。
ヨーロッパでのホップの痕跡(種子など)は、新石器時代、前ローマ時代、ローマ時代の北海沿岸の遺跡から発見される。遺跡当りのホップ痕跡が少ないので、ビール醸造に使われていた可能性は低い。ホップの遺跡数と遺跡当りの痕跡数が増えるのは中世前期からであり、中世盛期からホップの遺跡数は更に増え、痕跡数も多くなる。遺跡・痕跡調査から、ホップは遅くとも9世紀にはビール醸造に使用されていたと推定される。
ホップがビール醸造に使用されたと推定される9世紀以前から、様々の植物がビールのハーブとして使用されていた。遺跡調査での痕跡数から、ヤチヤナギが最もよく使用された植物であったことが判明している。ヤチヤナギは、ヤマモモ科ヤマモモ属の植物で学名はMyrica galeである。落葉小低木で、温帯地域の湿地に多く自生し、雌雄で株が異なる。現在でも、スコットランドや北欧、ドイツ北部の湿地帯に自生しており、手に入りやすいハーブである。すがすがしい独特の香りをもつ植物で、ハーブとして使用するときは、葉や枝、果実など植物全体を砕く。
ヤチヤナギは前ローマ時代のライン川北部河口付近の遺跡から発見され、その後のローマ時代、中世前期の多くの遺跡で多量の痕跡(小枝、葉、種子など)が発見されている。これらの遺跡のほとんどは、現在のヤチヤナギの自生地と一致している。その後、中世盛期からヤチヤナギを含んだ遺跡は少なくなる。このことから、ヤチヤナギは前ローマ時代から中世前期までビール醸造に盛んに用いられ、ホップがビールに使われだした中世盛期から衰えたと考えられる。
14世紀になると、北西ヨーロッパ全域で、ヤチヤナギビールが衰退した。その後、ヤチヤナギには毒性があるとの風説が流れ、北部ドイツでは、ヤチヤナギビールに罰金が科せられ、遂には禁止となった。こうした流れの中で、南部ドイツのバイエルンで1516年にビール純粋令が発布された。ビールに使用するハーブをホップだけに限定したのは、市民・領民の健康に配慮したためとも考えられる。なお、ヤチヤナギには毒性はなく、現在でもデンマークなどで一部の醸造所で、ビールに用いられている。
現在、ビールに使われているホップは、イラクサ目アサ科のフムルス属ルプルス種(Humulus lupulus)に属する。一時期、ホップはクワ科に分類されていたが、現在はアサ科に分類されている。フムルス属には、①ビール用ホップのH.lupulus種、②和名でカナムグラ(鉄葎)と呼ばれ、中国、台湾、韓国、日本にだけ自生しているH.japonicus種、③中国のホップ近縁種であるH.yunnanensis種の3種がある。また、ビール用ホップが属するH.lupulus種には、①ビール醸造用に栽培されているH.lupulus var.lupulus種、②日本の野生ホップでカラハナ草と呼ばれるH.lupulus var.cordifolius種、③北アメリカの野生ホップであるH.lupulus var.neomexicanus種三つの亜種がある。
ホップの核DNAと葉緑体DNAの塩基配列を解析して進化の道筋を探ると、フムルス属の中でのルプルス種(ホップ)とジャパニクス種(カナムグラ)の分化が約640万年前と推定された。また、世界各地の野生ホップを集めて解析すると、ヨーロッパ、北米、中国、日本の野生種集団は、遺伝的にも分化していることが判明した。ホップとカナムグラが分化した後、105-127万年前にルプルス種の中でヨーロッパ集団が分化し、その後、60-80万年前に北米、中国、日本の集団が分化したと推定された。日本はホップの故郷なのかもしれない。
ホップは、初冬に地上部が枯れる宿根性の多年生植物で、蔓性である。ホップには雌株と雄株があり、一般的には雌株を栽培し、未受精の毬花(花びらのように見えるのは、葉が変形した苞である)をビール醸造に用いる。受精した毬花は品質が下がるといわれており、ドイツでは雄株が発見されると伐採される。ホップは、地下の株で越冬し気温が上昇すると萌芽して蔓を伸ばす。ホップ畑には、棚が用意してあり、ホップの蔓は棚へ登る。腋芽からも蔓が伸びる。6月下旬から7月上旬に蔓が最上部に到達すると、毬花が咲く。毬花の開花期間は15-30日間で、ホップは8―9月に収穫される。

ホップ中の有用成分は、苦味質、精油成分とポリフェノール類である。ホップの苦味は、フムロン類と呼ばれる分子量360前後の複雑な化合物に由来する。フムロン類は水に溶けないので苦味が無いが、ビール醸造の過程で麦汁を殺菌する時、加熱により水に溶けるイソフムロン類に変化して、ビールに苦味をつける。苦味は人類が毒を持つ植物を食べないように備わった味覚であり、苦味を持つ植物は多かれ少なかれ、薬用植物であっても必ず毒性持っている。しかし、ホップのフムロンには、全く毒性がない。
ホップの精油成分の大部分は、イソプレン(炭素数5)を単位とするテルペノイド系物質である。テルペノイド系物質は、炭素と水素だけで構成されていて、麦汁やビールに溶解し難いので、ホップ精油は麦汁煮沸で蒸散して大きく減少する。このため、多くのホップ精油は、ビール中には検出できない。しかし、弁別閾値がμg/Lなので、ビールまで残った精油成分はビールの香味に大きく影響する。
最近、ニュージーランドやアメリカのホップから、特徴的な香りを持つ揮発性チオール類が発見された。揮発性チオール類とは、アルコールの-OH基が-SHに置き換わった化合物で、1990年代後半に、ソーヴィニオン・ブランワインから発見された。ワイン中の弁別閾値は、ng/Lと小さく、テルペノイド系物質の1000分の1である。ワインでは、シダを連想させる香りやグレープフルーツ様の香りの原因物質となっている。ニュージーランドのNelson Sauvinと言うホップにも、グレープフルーツ様の香をもつ揮発性チオールが見つかり、Nelson Sauvinで醸造したビールや発泡酒にも確認された。ビール中での弁別閾値は、70ng/Lと推定されている。その後、アメリカホップにも他の揮発性チオール類が発見された。
これまで、ドイツを中心とするヨーロッパホップでは、揮発性チオールが検出されなかった。チオールの-SH基がCuイオンと反応するので、防除にボルドー液を使用したドイツ産ホップには、揮発性チオールが含まれていない。同様に、銅釜を使った麦汁製造では、ビール中に移行しないことが予想される。ビール中での揮発性チオール類の発見が21世紀となったのは、揮発性チオール類の含有量がng/Lと微量であることと銅イオンの影響とが考えられる。
ホップは、新石器時代以前からヨーロッパで何らかの目的に使用されていた。中世初期からビールに使われ、その後、ホップはビールのためだけに品種改良され栽培されてきた。ホップは、毒性の無い苦味と精油成分と揮発性チオール類の香りを兼ね備えた植物だった。ホップがどのようにして極東からヨーロッパに伝わったのか、何故極東の人々はホップを忘れてしまったのか、この未解明の問題を考えるために、もう一杯苦いビールを飲もう。
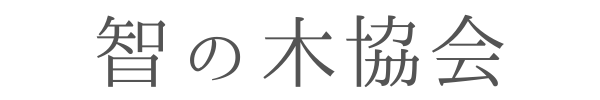
コメント