チャは、ツバキ科ツバキ属の常緑多年生木本で、学名(ラテン語名)をCamellia sinensisと言います。葉が小さく樹高が2〜3mほどの灌木で耐寒性の強い中国種と、葉が大きく8〜15mにもなる喬木のアッサム種が存在します。原産地としては、長江、メコン川上流域の中国の四川、雲南省からビルマ北部の山岳地帯と、中国東部から南東部にかけての二つの地域があるとする二元説と、長江、メコン川上流の地域のみとする一元説がありますが明確ではありません。中国種は、雲南、四川、貴州省などの中国西南部から福建、浙江省などの中部地域および台湾、日本の暖地などで栽培されており、インドやアフリカ(ケニアなど)、南アメリカ(アルゼンチンなど)へも移植されています。一方、アッサム種は、インドやスリランカ、インドネシアなどの熱帯、亜熱帯地域で栽培されていますが、徐々に味の良い中国種に代っているそうです。
チャの葉(茶葉)が初めて本草書に収載されたのは、唐時代に著された「新修本草」(659年)とされていました。しかし、それより160年程前に陶弘景が著した医学書「神農本草経集注」に、上薬として収載されている“苦菜”が茶葉であると記載されておりました。陶弘景の説は、賛否両論がありましたが、今日では肯定する意見が多数を占めています。さらに詳細な検証から、紀元前1世紀頃にはすでに茶葉が利用されていたと考えられております。当初、茶葉は薬用にされており、頭痛や目のくらみ、多眠、激しい口渇を治し、去痰、消化、利尿効果があり、解毒効果があって、下痢や二日酔いを治療するなどの薬効が知られていました。761年頃には、陸羽によって茶の専門書「茶経」が出版され、解熱作用や気鬱に効果のある事や、茶の種類、産地、品質、茶器、煮方、飲み方などの飲茶全般について記載されています。
日本には、近年の考古学的な調査などから奈良時代末期には渡来し、飲用されていたと考えられています。また、「新修本草」などの書物も渡来しているので、茶葉の薬効などの知識もすでにあったと思われます。一般的には、平安時代(805年)に唐から帰国した伝教大師最澄がチャの種子か苗木を持ち帰り、比叡山山麓の坂本に植えたことに始まると考えられています。「日本後記」には、815年4月に嵯峨天皇の近江行幸の折、大僧都永忠が梵釈寺において茶葉を煎じて献上したと記されており、これが日本最初の喫茶の記録になります。嵯峨天皇は、815年6月に畿内の諸国にチャの栽培を命じられました。また、平安宮に茶園を設けられ、内蔵寮薬殿で製茶が行われたそうです。当時の喫茶は、団茶(茶葉を蒸してから臼で搗いて固めて乾燥したもの)を研って粉末にして湯に投じて煮だしたものを飲んでおりました。団茶は、今日の雲南省のプーアル茶や高知県の碁石茶の原型と言われていますが、著者にはあまり美味しいものとは思われません。それでも唐風文化にあこがれる平安貴族の間に団茶を用いた喫茶が流行したことは、「凌雲集」などの漢詩集に菅原道真などの宮廷人の茶を讃える詩が残っていることから伺い知ることができます。しかし、遣唐使の廃止などから唐風文化が廃るに従い、喫茶の風習は寺院などでの儀式や行事に用いられるに過ぎず、日常的に飲用されるまでには至りませんでした。
喫茶の再興は、鎌倉時代の初期(1191年)に南宋から帰国した千光国師栄西によってもたらされました。栄西禅師は、当時の中国で広まっていた抹茶を用いた新しい茶法(抹茶喫茶法)とともに、種子や苗木を持ち帰ったと考えられています。それらは九州の備前や筑前に植えられるとともに、さらに山城栂尾にある高山寺の明恵上人に贈られ、栂尾の茶は“本茶”と呼ばれ最高品質との評価を得ていました。栄西禅師の著した「喫茶養生記」にもあるように、当初は薬としての用法が中心でしたが、栽培が普及するとともに嗜好品として飲まれるようになっています。貴族社会の遊びとして闘茶(茶の味を飲み分けて勝敗を競う遊び)なども行われましたが、聖一国師円爾や大応国師南浦紹明によって中国の茶会の作法や茶道具などが紹介され精練されていきました。室町時代には次第に華やかさより精神的交流を重視した日本独自の“茶の湯”へと発展し、武士などの支配階級に広がりました。江戸時代初期(1654年)に黄檗宗の華光大師隠元が明国から来日し、煎茶喫茶法がもたらされました。幕府の「慶安御触書」などで喫茶が贅沢とされたにもかかわらず、庶民の間にも煎茶が広く飲まれるようになりました。明治時代になると茶の湯は“茶道”と改称され、一般人の礼儀作法の嗜みとなるまでに発展しました。
今日では、加工調製法の異なるいろいろな種類の茶がありますが、不発酵茶と半発酵茶、発酵茶の3種に大別できます。不発酵茶は緑茶のことで、発酵を止める方法が異なる日本式の蒸茶と中国式の釜入り茶に分けられます。蒸茶には、栽培時の遮光や加工時の揉捻の有無、摘採部位の違いなどによって玉露、抹茶(碾茶)、煎茶、番茶などがあります。半発酵茶は、烏龍茶に代表されるもので、摘採後に放置して乾燥過程で茶葉自体に含まれる酵素で発酵させるなどしたものです。類似のものとして弱発酵茶(白茶)や弱後発酵茶(黄茶)が中国にあります。発酵茶は完全発酵茶や全発酵茶とも呼ばれ、紅茶がその代表と言えます。このほか、後発酵茶(黒茶)と呼ばれる、緑茶をコウジカビなど微生物で発酵させるものがあり、プーアル茶が有名です。
2010年における世界の茶葉生産量は、約452万トンで、1位が中国の150万トン、2位がインドで100万トン、3位がケニアの40万トンになっています。そのうちの約80%が紅茶にされ、残りの約20%が緑茶で、烏龍茶などの茶は微量にすぎません。日本では、8.5万トンが静岡、鹿児島、三重、宮崎、京都などで煎茶や番茶として生産されています。
茶葉には、カフェイン、カテキン類およびテアニンなどのアミノ酸類が主要成分として存在し、香り成分のテルペノイド類やフェノール類、フラボノール類およびサポニンも含有されています。カフェインには、中枢興奮による覚醒作用と強心作用、呼吸量と熱発生の増加による脂肪燃焼効果、脳細動脈収縮作用、利尿作用などが、カテキン類に、抗酸化作用、抗菌、抗ウイルス、抗う蝕作用、抗がん作用、抗糖尿病作用、抗肥満作用、血圧上昇抑制作用などが、テアニンには、リラックス効果、抗ストレス効果、睡眠改善作用などが報告されています。
筆者らは、生体機能性物質の開拓を志向して、チャの各部位について化学と薬理の両面から研究を進めており、日本産中国種茶葉からサポニン(foliatheasaponin類)、スリランカ産アッサム種茶葉からサポニン(assamsaponin類)を単離、構造決定するとともに、茶葉の伝承薬効の解毒作用に関連してサポニン成分にマスト細胞からの脱顆粒抑制活性を見出しています。また、チャの花 (茶花) は、中国やインドなどの茶の主産地でも食経験は無いが、日本では何故か古くから食用にされており、例えば島根県の“ぼてぼて茶”という茶花の入ったお茶漬けのような料理は今日も出雲名物となっています。しかし、茶花の薬効は伝承されておらず、また含有成分や生体機能についても全く研究されていません。“ぼてぼて茶”がタタラ(製鋼)職人などの重労働者の空腹時の凌ぎ飯や飢饉の際の食延と呼ばれる食料消費の節約をはかる救荒食であったことに着目して、食欲抑制や吸収阻害効果を中心に検討しました。その結果、主成分であるサポニン [chakasaponin 類 、floratheasaponin 類など] に摂食抑制、脂質および糖吸収遅延、胃排出能抑制、小腸運動亢進および抗肥満作用などが認められました。サポニン成分の定量分析や安全性試験および臨床結果などからメタボリックシンドローム予防に有用な機能性食品“茶花”が開発されました。
人参などのサポニン成分は水溶性で高分子量の配糖体であり、そのままの型では吸収されず、腸内細菌によって加水分解や構造変化を受けて血中に移行して作用発現することが明らかになっていました。茶花のサポニンは、経口投与で迅速に活性発現し、また、アシル基の除去や結合位置の転位によって活性が消失することから、腸内細菌の関与は考えられません。作用機作を検討したところ、例えば摂食抑制作用は、消化管内で食欲亢進シグナル neuropeptide Y (NPY) の分泌減少と食欲抑制に関与する serotonine (5-HT) などの神経メディエイターや消化管ホルモンの cholecystokinin (CCK)、glucagon-like peptide 1 (GLP-1) などの遊離促進を発現して迷走神経求心路を介して作用を発現することが明らかとなりました。茶花サポニンの結果は,水溶性成分が代謝吸収されることなく消化管での神経刺激によって作用発現することを示唆しており、湯液や水抽出エキスが用いられる生薬や漢方方剤の薬効解析に有用な知見になると考えています。
以上のチャの持つ智的な背景と私のチャ研究の経緯から智の木協会に入会するにあたり、チャを選択しております。
(平成29年2月28日)
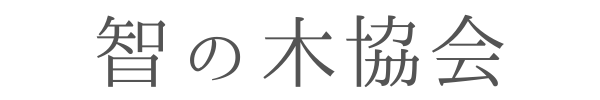

コメント